解説「菩薩の生き方」第二十三回(4)
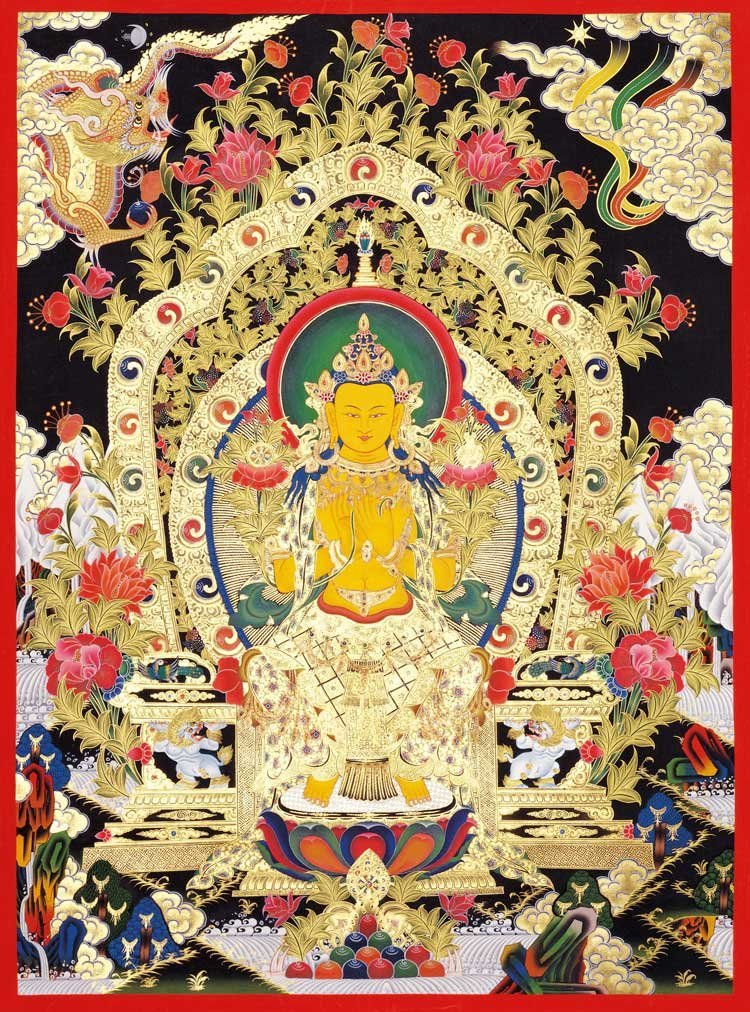
はい。ちょっと話が大きくそれましたけども、そのようなかたちで、ある時期から、アーサナや呼吸法、ムドラー、マントラ等の、心だけではない、つまりこの肉体とか、あるいは呼吸とか、あるいはこの声を使った修行がいろいろ生まれてきたと。つまりそれくらいやらないとなかなか大変な時代になってきたと。で、現代はさらにそれから下った時代ですから、だからいつも言うけども、カイラスでも修行法はいっぱいありますよね。もういろんなタイプの修行法があると。でも逆にそれはそれで面白くていいですよね(笑)。いろんな修行ができて楽しいなと。うん。そういうのもあるし、もちろんそれによって、さまざまなパターン――つまりさ、菩薩道とかバクティの道を行く場合は、壮大な話になるけど、一生じゃ終わらないからね。つまり何生も何生も――何生もっていうよりも、もう数えきれないほどの生を輪廻し――つまり単純に『ヨーガスートラ』のように心を止めて真我を悟ればいいだけではなくて、菩薩として、バクタとしてのスキルを、つまりあらゆる状況においても人を救うとか、あらゆる状況においても悟りを得るような、さまざまな内的スキル、内的能力を高めなきゃいけないんだね。その意味ではとても素晴らしいとも言える。
これもいつも言ってるけど、この現代はカリユガ、暗黒の時代、悪しき時代っていうわけだけど、その別の考え方として、いや、暗黒の時代だからこそ、この時代には――つまりこの暗黒の時代は、普通の修行では救えないと。つまり昔のインドみたいな、昔のサティヤユガとかの時代は、もう修行しやすい、解脱しやすい時代だったから、あまりテクニックはいらないと。「はい、座って神に心を集中しましょう」――パーッ!――これで終わりであると(笑)。ね。で、現代ではそんなことは全くできないと。あるいはある程度前の、数百年とか千年とか前に通用した修行も、それだけでははなかなか難しい時代になってきたと。よってこのカリユガには、まさに最高の、あるいは秘密の、このようなものすごい重りを付けてるような時代でも救われるような法が降りるっていうんだね。で、その代表が例えばバクティヨーガであり、あるいは密教であると。
よって、賢者たちは、カリユガに生まれることを望むっていうんだね。カリユガに生まれれば、そのような高度なっていうか、最高の秘儀が降りてくるから。だからその意味ではわれわれはそれは喜ばなきゃいけない。つまり現代ではいろんな修行を伝授され、で、それを学ぶこと、修行することによって、多くの、いろんなタイプの、修行者としての、あるいは菩薩としての、バクタとのしての、スキルがね、身に付いていくんだと。
ちょっと話がずれるけど、まあこれも何度か言ってるけど、皆さんがやってる気功、つまり易筋経っていうやつね、あの話も同じですよね。あれも聞いたことあると思うけど――まあ伝説ですけどね。伝説によると、仏教の、お釈迦様から連なる――一応お釈迦様の一番弟子はサーリプッタっていう人がいたんだけど、このサーリプッタともう一人モッガッラーナっていう人は二大弟子だったんだけど、ただこの二人はお釈迦様より早く亡くなってるんですね。で、お釈迦様が亡くなって、そのあとを継いだのがマハーカッサパ。マハーカッサパがまあ、ある意味では二代目教祖みたいになったわけだね。で、そういう感じで正統的な仏教の教祖がまあ一応いて、で、その二十何代目かの人がボーディダルマ。日本でいう達磨さんですね。達磨大師、ボーディダルマっていう人だったらしくて。このボーディダルマが中国に教えを説きに行きましたと。教えを説きに行ったっていうか、まず中国に行って、まず自分の修行を完成させたと。で、そのときにボーディダルマがやった修行は、まさに心の修行。彼は洞窟にこもり、洞窟の壁の方を向いて、そのまま――もちろん食事とかはしただろうけど、あとはひたすら九年間瞑想し続けたっていうんだね。テクニック何もなし(笑)。ひたすら自分の心への集中を九年間続けたと。で、それで悟りを得たと。で、悟りを得て、それを中国の人たちに伝えようとしたんだけど――弟子がいっぱい集まってきたと。で、自分がやったようなひたすら超集中の――いわゆるこれが禅なんですけどね――それを伝えようとしたら、なかなかみんな修行が進まないと。なんでかっていうと、それ以前にみんな肉体が駄目だったと。逆にいうとこのボーディダルマは肉体は強かったんでしょうね。まあ実際にはどういう人だったかわかんないけどさ、いろいろ絵に描かれる達磨さんって、達磨大師って、強そうだよね、ちょっとね(笑)。ヒゲが生えてちょっとガタイがいい感じで。多分インドから来て――しかも、ね、易筋経みたいなのを教えるぐらいだから、おそらく、ハタヨーガ的なものをやってたかどうかはわかんないけども、インドにもともと伝わってるインド武術、カラリパヤットとか、あるいはアーユルヴェーダ的な考え方、あるいはまあなんらかのインドの古代的な心身の鍛錬法とかやってたのかもしれない。
とにかくその中国の弟子たちはちょっと体が弱いと。あるいはもっと言えばエネルギー的に弱いと。それからおそらく気道も詰まってると。よって、そもそもそのような、例えば九年間集中し続けて悟るような高度なことができる器を持っていなかったと。よって達磨大師は「これじゃ駄目だ」と。「これじゃ駄目だから、まず体から鍛えなきゃいけない」と。ね。あるいは気道から通さなきゃいけないと。そこで達磨大師が組み立てて、中国の弟子たちにやらせたのが、この易筋経だといわれています。
もちろん易筋経にはいろんなバージョンがあって――っていうのは、かなり昔のことだからね、そこから伝わってくる間にいろんな付け加えや、あるいはちょっと整理されたりして、いろんなバージョンがあるんだけどね。だからここでも、まあ今日やった易筋経や、あるいは武易筋経とかいろいろあるけども、そういうのが広まっていったと。
だからこれも全くベクトルとしては同じね。まさに達磨大師が、自分ではできた心だけの修行が弟子にはできなかったと。よって、しっかりと肉体および気の流れ等から、あるいは生命力等からちゃんと整えていくことが大事だっていうことで、どんどんそういうのをやらせるようになったといわれている。
だからこれはもう時代としてもしょうがないんでしょうね。どんどんどんどんけがれた時代になってる。あるいは肉体もどんどんどんどん弱り――ヴィヴェーカーナンダも別の観点からそういうこと言ってますよね。ヴィヴェーカーナンダも、何度も言うけども、まずインド人たちは、もうちょっと肉体が弱ってるから、体から鍛えろと。今のインド人には『バガヴァッド・ギーター』よりもサッカーの方が必要だと。ね(笑)。これ冗談っぽく言ってるんだけどね。つまりもうヨボヨボっていうか、気が詰まってる、エネルギーもない体で、言葉だけ『バガヴァッド・ギーター』とか読んでるよりも、まずはサッカーでもして、ちょっとリフレッシュして、体を鍛えて――あと、そういうことをヴィヴェーカーナンダが言ってる話の中でさ、「まずはインド人は体を鍛えなきゃいけない」と。「わたしが今でも毎日ダンベルで体を鍛えてるのを知らないか」とか書いてあって(笑)。「いや、知らないよ」って感じなんだけど(笑)。
(一同笑)
わたしもそれを見て、「え、そうだったんだ」って。ヴィヴェーカーナンダは毎日こうダンベルやってたって(笑)。
(一同笑)
まあ確かにヴィヴェーカーナンダは強そうですよね、ちょっとね。まあヴィヴェーカーナンダはスポーツも万能だったっていうから、ヴィヴェーカーナンダは別にいいんだろうけど、当時のインド人たちがちょっと肉体が弱っていたと。だから、「健全な体に健全な精神は宿る」っていう言葉があるけども、実際には肉体が強いからって心もいい状態になるとは限らないが、でも少なくとも強い、あるいはエネルギーにあふれた心はまあできやすいよね。しっかり体の気が通ってて生命力があふれてたら。で、その素晴らしい心の力を使って修行しなきゃいけないと。
はい。もちろん単純に体の力を強くするだけではなくて、まとめるけども、しっかりエネルギーを通すと。あるいはマントラを使ってバイブレーションをきれいにすると。あるいは呼吸法を使って――これもよくヨーガの講習会とかで言う話だけど、われわれの生命活動っていうのはすべて連動してると。例えばわれわれが心がドキドキしてるときは呼吸も荒くなると。あるいは心拍数も早くなってきて、あるいは自律神経も狂ってくると。でも心が安定してるときは呼吸も安定し、心臓も安定し、神経も整うと。つまりこの連動があって。で、この連動してる中で、われわれが唯一というか最も手が出せるのは呼吸であると。われわれは心臓を自分でコントロールすることはできない。ダッダッダッダッダッダッダッて心臓が速くなってるときに、ピッて押して「ダッ……ダッ……」ってなることはできないですよね。まあただクンバカではできるけどね。グーッて力を入れたクンバカによって心臓の動きを正常にするっていうことはできるけども、それはちょっと特殊な技みたいなもので、普通はできないと。あるいはもちろん自律神経をコントロールするなんて普通はできない。精神のコントロールも非常に難しいと。しかし呼吸のコントロールは簡単だよね。今日もやった呼吸法のように、つまり、ゆったりと吸って、止めて、吐きましょうと。これをやるのは簡単であると。で、これをやることによって、連動してる心臓も整い、神経も整い、精神も整ってくると。このテクニックを活かしてるのがこの呼吸法ですよね。
『サーダナーの指針の花輪』とかを書いてるあのシヴァーナンダっていう人は、何度も言うように、あの人もインテグラルヨーガっていって、いろんなヨーガをしっかりと統合的に現代ではやらなきゃ駄目だって言ってる人なんだけど。ただあの人もちょっと、なんというかな、いろんな角度から説いてるからさ、その説き方によっては、あるときはジュニャーナヨーガ的なものをすごく称賛し、あるときはバクティヨーガを称賛し、みたいな感じなんだけど。で、あるところで、例えばちょっと辛辣な言い方をしてね、「呼吸を整えることによって心を整えていく――これは愚鈍な者の道である」とか書いてあるんだね。愚鈍な者。つまり、本来はそんなの使わなくて、呼吸法なんかやらず、体操もやらずに、グーッと集中して悟りを得られれば最高なわけだよね。だから、「それができない愚鈍な者には呼吸法がある」とか書いてあって(笑)。ちょっと辛辣な言い方なんだけど、でも、そういうことなんです。つまりみんな今、愚鈍なんです。全員愚鈍(笑)。全員愚鈍だから、やはり呼吸法とかアーサナとか気功とか、そういったものはまあ最大限に活用しなきゃいけない。
まあもちろん愚鈍っていうだけじゃなくて、外的な要因も大きいからね。つまり現代では人も多いから、普通に町を歩くだけで気が詰まってくると。あるいはエネルギーもロスすると。このような状態ではやはり、まずそれを復活させることから始めなきゃいけないよね。例えば仕事して家に帰ってきたら、もうエネルギーが落ちてると。あるいは疲れてると。気も詰まってると。その、愚鈍とかいうよりも、まずマイナスの状態になってるから。それをまず戻すことから始めると。ね。例えばムドラーとかまあいろいろやって、しっかりとその気の流れを戻し、で、かつそれプラスアルファとして優れた瞑想ができるように、さまざまなテクニックを使わなきゃいけないと。これが現代のパターンだね。
-
前の記事
解説「菩薩の生き方」第二十三回(3) -
次の記事
解説「菩薩の生き方」第二十三回(5)




