解説「菩薩の生き方」第二十三回(5)
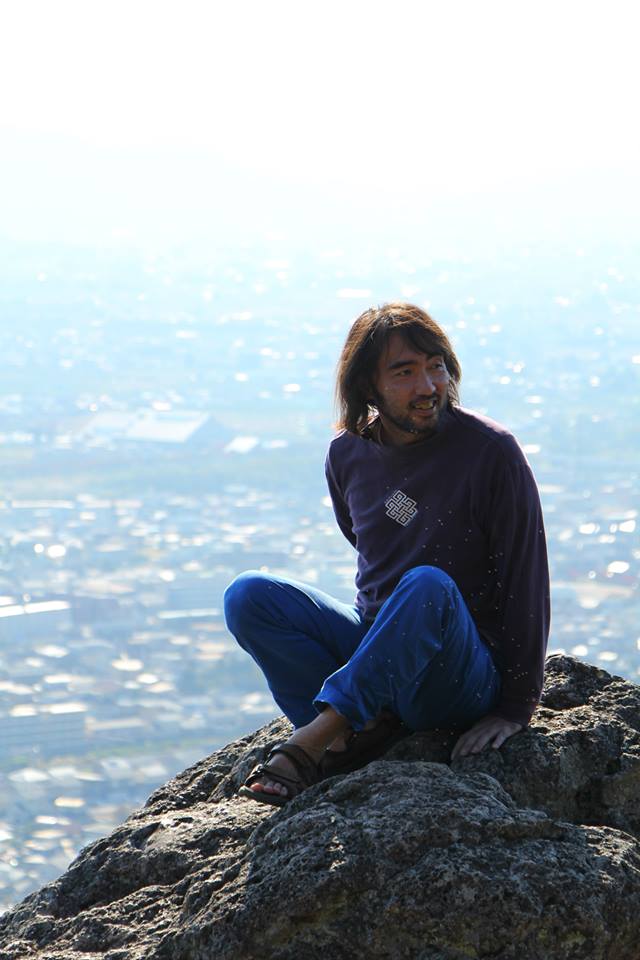
「しかし体の修行も言葉の修行も、あくまでも心を浄化し、鍛え、調御するという目的のために組み立てられているということを忘れてはいけません。もしその心という部分をおろそかにし、体と言葉の修行だけを続けても、修行の成就を得ることはできないでしょう。逆に、もし心が速やかに調御されるなら、体と言葉の修行がなくても、すべての修行を成就することができます。よって心こそが最も重要なのだ、というのがこの最初の詩の意味合いです。」
これはわかりますよね。まあ、ポイントを間違うなっていうことだね。あくまでも、最高のっていうか、最も注目しなきゃいけないのは心であって。しかし何度も言ってるように、心の修行だけでは駄目な時代になってきたから、われわれはいろんな修行を今生ではやらせてもらってると。しかしその意味合いっていうかな、なんでそれをやってるのか、あるいは最も大事なのは心であるっていうことを忘れてただ格好だけやってたとしても――そうですね、皆さんはもうそのような、システム的な形の修行はもう十分に与えられてる。だからあとはもう皆さんの心次第っていうことになるよね。つまり、日々教えを学び、教えどおり生きると。教えの理想に心を近づけていくと。
これはもちろんさ、詞章を読んだり、あるいは礼拝をしたり――によって、当然、自然に変わっていく部分はありますよ。すべてデータだからさ、まあ歌とかもそうだけど、「おれはおれだ」「おれはエゴの塊だ」と。「俺は人のことなんかどうでもいいんだ」「慈愛とかわかんねえよ」とか言ってた人も、毎日毎日、「衆生の~」とか(笑)、毎日歌ってたら、ちょっと変わってくるよね、やっぱりデータによって。やっぱり人のことを考えなきゃいけないのかな、とかね。それはそれであります。それはそれであるんだけども、そのようなシステム的なものだけではやはり弱いね。やっぱりわれわれの「そうなりたい」っていう気持ち、あるいは「そうしよう」っていう気持ちがやはり大事です。「わたしはまだまだエゴが強い」と。「だから日々の中でできるだけエゴをなくしていって、人のために生きられるようになりたいんだ」と。「わたしはほんとの意味でもっともっと慈愛の持ち主になりたいんだ」と。そして「いろんな場面にぶち当たったときにそのようにしよう」と。「頑張ってここではエゴを滅して、相手のためを考えた行動を取ろう」とかね、そういった心の働き。
そして、もう一回まとめるけども、それこそが修行であり、そして日々の形ある修行はそれを助けてくれるものなんだと。この感覚ね。これを忘れないようにする。それを忘れちゃって、日々詞章を唱えてると。マントラを唱えると。ムドラーとか行法をやると。それが、もう一回言うよ――正しい心をつくっていくっていうことの補助だっていうことを忘れちゃうと、いったいなんのためにやってんのかわかんなくなる。
でも、繰り返すけど、それだけでも修行進みますよ、実際は。自然にね、進むけども、ね、本来これはなんのためにやってんの?っていうのを忘れちゃうと、当たり前ですけど、進み方は遅いと。はい。
-
前の記事
解説「菩薩の生き方」第二十三回(4) -
次の記事
心を決して変えないようにしよう。




